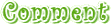[PR]
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
300ss お題:色『二〇一七/〇五/〇六』
お題:色
タイトル:『二〇一七/〇五/〇六』
ジャンル:オリジナル
注意:考察教室スピンオフ
研究室を訪れると、恩師が通常よりにぐんにゃりしていた。
原因は机の上に置かれた原稿用紙だろう。
「どうしたの、それ」
用紙は白紙。
「地域雑誌に<色>と<文学>を絡めて何か書いてくれって……」
「谷崎とかは? 書き易そうじゃん」
「いいけど、一般向けしないしなぁ」
谷崎潤一郎は優れた作家だが、誰もが一度は読んだ事がある程作品は一般的ではなく、作風もマニアックな傾向だ。
「じゃあ、宮沢賢治?」
「賢治か、いいね。青をテーマに……」
「え、あ、色彩の方……?」
「あのね、アレをどう一般向けに書くの?」
遺品として出てきた、賢治のコレクションの事だろう。
確かにそっちの<色>だと、谷崎よりもマニアックになるな、と村上も思った。
=======================================
拙作『江戸川悠の考察教室』のスピンオフ作品です。
キャラなど分かりにくくてすみません。
宮沢賢治は生涯独身(かつDTという説もある)で、熱心な仏教徒(法華教)でした。
作風も純粋で、子供のような鋭敏な感性を持つ作家です。
しかし、彼の死後、遺品からは大量の春画が発掘されたそうです……。
やめてさしあげて……。と、思いつつも、賢治の意外な一面を知る良い資料でもあります。
色彩の方の色については、賢治と言えば<青>です。
有名な『春と修羅』の冒頭文、
わたくしといふ現象は
仮定された有機交流電燈の
ひとつの青い照明です
に代表されるように、とにかく青色が作品に出てくることが多いです。
そこに注目しながら作品を読んでみるのもいいかもしれません。
賢治が青という色に込めた、色彩としての青以外のメタファーを読み取れるかもしれません。
また谷崎も、色彩という意味の色の方でも、言わずもがな優れた作家であります。
彼の作品の中に登場する着物を再現した展示や、『細雪』の舞台の四姉妹の衣装を見ると、谷崎潤一郎という作家の美的感覚に圧倒されますよね。

 管理画面
管理画面